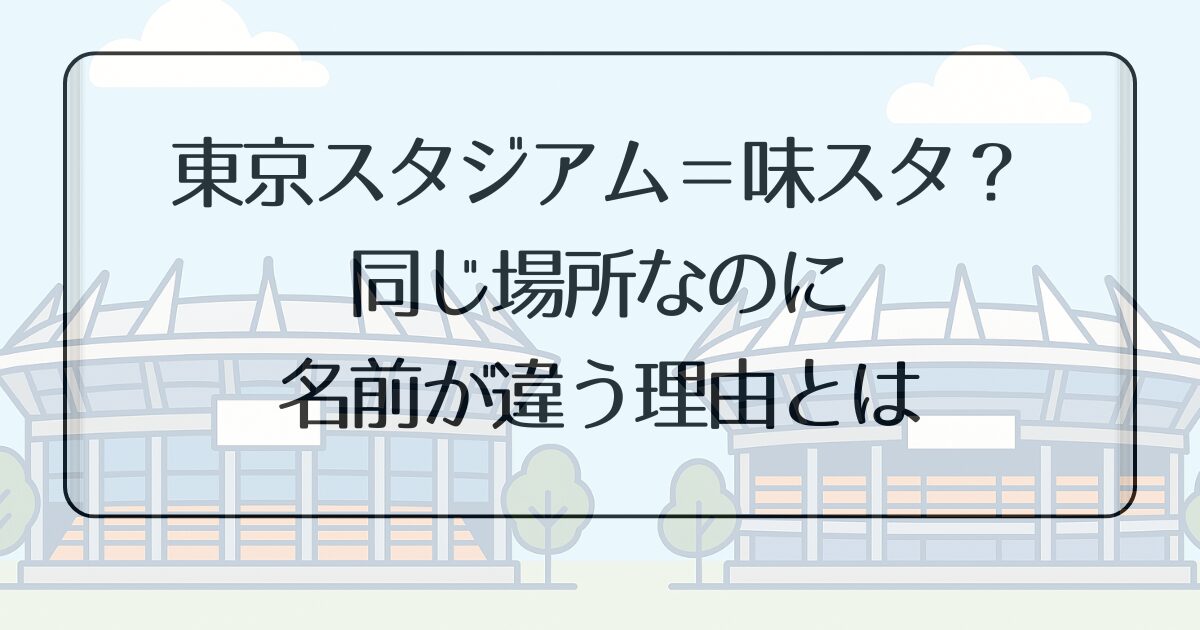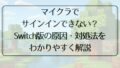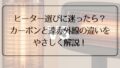「味スタ」として親しまれる味の素スタジアム。実は、正式名称が「東京スタジアム」だということをご存じでしょうか?東京郊外に位置しながらも、首都圏を代表する多目的スタジアムとして多くの人々に愛されています。
同じ場所を指しているのに名前が違うのは、企業スポンサーによる“ネーミングライツ(命名権)”が関係しています。こうした制度によって、企業が地域社会と結びつき、運営や維持管理に貢献する仕組みが生まれました。
この記事では、正式名称と愛称の違い、命名権の背景、名称の由来、そしてJリーグ2クラブの本拠地としての活用まで詳しく解説します。
さらに、スタジアムの歴史的な建設経緯や地域との関わり、コンサートやイベントでの活用など、幅広い角度から「味スタ」の魅力を紹介します。
スポーツだけでなく、コンサートや地域イベントの場としても親しまれる「味スタ」の魅力を、歴史とともに見ていきましょう。
味の素スタジアムと東京スタジアムの違いとは?

まずは、2つの名称の関係性を整理してみましょう。
実は同じ施設を指している
「味の素スタジアム」と「東京スタジアム」は、実は同じ建物を指しています。つまり、施設の構造も利用目的も共通しており、運営主体や所在地も完全に一致しています。
東京都調布市西町の広大な敷地に建てられ、約5万人を収容できるスタンドや最新の照明・音響設備を備えた本格的な多目的競技場です。
サッカーの試合だけでなく、陸上競技や大型イベント、コンサートにも対応できる設計がなされており、訪れる人々に快適で安全な観覧環境を提供しています。
また、周辺には緑地や公園も整備されており、地域住民の憩いの場としても親しまれています。都心からのアクセスも良好で、東京の新しいランドマーク的存在として愛され続けているのです。
「東京スタジアム」が正式名称、「味の素スタジアム」が通称
正式名称は「東京スタジアム」ですが、企業スポンサーである味の素が命名権を取得したことで「味の素スタジアム」という愛称が付けられました。
この契約は当時としては画期的な試みであり、行政と企業が協働して地域のスポーツ文化を発展させる新しい形として注目を集めました。味の素は単なる名前の提供にとどまらず、スタジアムの運営やイベント支援、食育活動などを通じて地域貢献にも積極的に関わっています。
また、企業イメージである「食と健康」を象徴する場として位置づけられたことで、スタジアム全体に温かみのあるブランドイメージが定着。スタジアム名が掲げられた看板やグッズ、チケットデザインなども統一され、来場者の印象に強く残る演出がなされました。
こうした背景から、「味の素スタジアム」は単なる呼称を超えて“地域と企業をつなぐシンボル”となったのです。
「味スタ」と呼ばれるようになった経緯
略称の「味スタ」は、ファンやメディアの間で自然と使われるようになり、今ではすっかり定着しています。
さらに、SNSやニュース番組、スポーツ中継などでも頻繁に使われるようになったことで、その呼称は全国的に広まりました。
特にサッカーファンの間では「味スタ」といえば東京のホームスタジアムを指すほど浸透しており、地域や世代を問わず愛される言葉となっています。
また、スタジアム周辺の商業施設やイベントチラシなどにも「味スタ」という略称が積極的に使われており、地域ブランドの一部として定着しました。この親しみやすさが、施設そのものの認知度を高める要因にもなっています。
国際大会では「東京スタジアム」と表記される理由

Jリーグでは「味の素スタジアム」として知られるこの会場ですが、実は国際大会になると「東京スタジアム」として、アナウンスや表記をされるのをご存知ですか?この違いには、スポンサー契約や国際ルールが関係しています。
FC東京の公式サイトにも「東京スタジアム」という表記があり、これは単なる通称ではなく、国際大会で使用される正式な名称としての役割を担っています。
国際サッカー連盟(FIFA)やアジアサッカー連盟(AFC)などが主催する大会では、広告とみなされる名称の使用が制限されるため、ネーミングライツによる愛称(例:「味の素スタジアム」)ではなく、本来の施設名である「東京スタジアム」が使用されるのです。
つまり「東京スタジアム」は、スポンサーの都合ではなく、国際大会における公平性や中立性を保つためのルールに基づいた名称使用であることが分かります。
東京スタジアムの名称の由来と建設の背景
「東京スタジアム」はどのような経緯で誕生したのでしょうか。
建設は2001年、東京都と調布市による共同整備
東京スタジアムは2001年3月に開業。東京都と調布市が共同で整備し、スポーツ・文化の拠点として計画された施設です。
建設当時は、東京周辺で国際規模の大会を開催できるスタジアムが限られていたため、新たに“多目的で柔軟に利用できる施設”が求められていました。
設計段階では、観客席からの視認性や安全性、バリアフリー設計に特に配慮し、老若男女が快適に観戦できるよう工夫がなされています。
また、スタンドの角度や高さを調整することで、どの座席からでもピッチ全体を見渡せる構造となっており、臨場感を重視した設計が特徴です。
地元の雇用創出や地域経済の活性化にもつながり、完成当時から「東京の新たなスポーツ文化の中心地」として期待を集めました。
施設完成後は、市民イベントや教育活動にも活用され、まさに地域とともに成長してきたスタジアムといえます。
首都圏を代表する多目的競技場として計画
当初からサッカーを中心に、コンサートやイベントにも対応できる多目的スタジアムとして設計されました。その設計コンセプトには、「誰もが楽しめる都市型スタジアム」という理念が込められています。
ピッチの芝生は年間を通して最適な状態を保つよう管理され、天候や季節を問わず利用できるよう最新の排水・照明システムを導入。音響設備も国内トップクラスで、コンサートでは臨場感のあるサウンドを体感できます。
また、バックステージや搬入口などイベント運営面にも配慮が行き届いており、演出の自由度が高いのも特徴です。観客動線や売店エリアのレイアウトも工夫され、来場者が快適に過ごせるよう設計されています。
このように、スポーツとエンターテインメントの両面で活用できる“首都圏のシンボル的スタジアム”として、幅広い支持を集めているのです。
「東京スタジアム」という名称に込められた意味
「東京を代表するスタジアムにしたい」という想いが込められています。この名称には、首都・東京の顔として世界中の人々を迎え入れる意志や、都市文化の象徴としての誇りが込められているのです。
単なる地名ではなく、東京が持つエネルギーや多様性、そして未来への希望を体現する場として名付けられました。
また、「東京スタジアム」という響きには、国際大会やコンサート、地域イベントなど、あらゆる人々をつなぐ“交流の舞台”という意味も含まれています。
さらに、設計者や行政担当者の間では、シンプルかつ覚えやすい名称によって市民に親しまれる存在にしたいという願いもあったといわれています。
この思いが現在も受け継がれ、東京スタジアムは地域の象徴としてだけでなく、国内外のスポーツファンにとっての特別な場所となりました。
国立競技場改修前の代替会場としての役割
国立競技場の改修期間中には、多くの大会を受け入れる代替会場としても活躍しました。
当時、国立競技場は全面的な建て替え工事に入っており、国内外のスポーツイベントの開催場所が限られていました。その中で東京スタジアムは、アクセスの良さや設備の充実度から代替会場として最適と判断され、多くの競技団体や主催者に選ばれました。
サッカーだけでなく陸上、ラグビー、学生大会など、さまざまなイベントを柔軟に受け入れ、工事期間中の東京のスポーツ文化を支える重要な役割を担いました。
また、この期間に多くのスタッフが大会運営ノウハウを蓄積し、その後のイベント開催力の向上にもつながりました。
観客からも「臨場感がある」「アクセスしやすい」と高い評価を得て、結果的に東京スタジアムの知名度と信頼性をさらに高める契機となったのです。
味の素が命名権を取得した経緯と目的
開業から2年後、「味の素スタジアム」という名称が誕生します。その背景を見てみましょう。
2003年、味の素が初の命名権取得企業に
2003年に味の素株式会社が東京都と契約を結び、命名権を取得。「味の素スタジアム」が正式に誕生しました。
この契約は、当時の日本ではまだ珍しい取り組みで、企業が自治体と連携して公共施設の名称を担うという新しい形を示した事例として注目されました。
契約にあたって味の素は、単に自社の宣伝のためではなく、地域と共に発展していく“共創”をテーマに掲げ、イベント支援や地域の健康啓発活動などを通じて地元への貢献を約束しました。
さらに、スタジアム内の売店では味の素製品を使ったメニューを提供するなど、企業ブランドと施設運営が自然に融合する形を実現。こうした取り組みは、のちに全国各地で広がる命名権ビジネスの先駆けとなり、「味の素スタジアム」は日本のネーミングライツ文化を象徴する存在となったのです。
契約金額や期間(例:5年更新制)
契約は数年ごとの更新制で、金額はおよそ数億円といわれています。命名権料には、施設の維持管理費や地域イベントの開催支援費なども含まれており、単なる名前使用料にとどまらない仕組みとなっています。
また、契約期間中には東京都と味の素の双方で定期的な協議が行われ、スタジアムの運営方針やイベント内容の方向性などを確認し合う場が設けられています。
更新の際には地域住民からの意見や利用者満足度も考慮されるなど、透明性の高いプロセスで契約が継続されています。このような取り組みにより、スタジアムは行政・企業・市民が一体となって支える施設として発展しているのです。
「食と健康の企業」としての地域貢献を目的に
味の素は単なる広告ではなく、地域社会とのつながりを重視し、スポーツ振興や健康啓発にも関わっています。
その取り組みの一環として、地元の小中学校への食育授業の提供や、スタジアム内外での健康イベントの開催も行っています。
例えば、親子で参加できる料理教室や、アスリートによる栄養指導セミナーなどを通して、「食を通じて健康を支える」という企業理念を地域に浸透させてきました。
また、試合開催時には地元商店街と連携したフードフェスやフェアも実施され、地域経済の活性化にも寄与しています。こうした活動を継続することで、味の素は単なるスポンサーではなく“地域に根ざしたパートナー企業”としての信頼を確立しました。
企業と市民、そしてスタジアムが一体となり、東京のスポーツ文化を支える存在へと成長しているのです。
契約更新でブランドとして定着した「味スタ」
契約更新を重ねることで「味スタ」は東京を代表するブランドとして定着しました。
契約のたびにスタジアムの運営方針やイベント内容がブラッシュアップされ、味の素のブランド価値と地域文化の双方が進化してきました。
更新ごとにロゴデザインや施設内サインのリニューアル、イベント協賛の拡大などが行われ、来場者にとっても新しい発見のある空間へと発展。結果として「味スタ」という名称は単なる愛称を超え、東京のスポーツとエンターテインメントを象徴する存在となりました。
味の素スタジアムの位置とアクセス情報
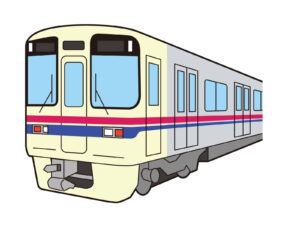
実際に訪れる際に知っておくと便利な立地情報を紹介します。
所在地と最寄り駅
東京都調布市西町376-3にあり、京王線「飛田給駅」から徒歩5分です。
イベント開催時は臨時改札も開設されます。駅からスタジアムまでは案内板や誘導スタッフが配置されており、初めて訪れる人でも迷うことなくアクセスできます。
周辺にはカフェやコンビニ、軽食を楽しめる店舗も多く、試合前後に立ち寄るファンの姿もよく見られます。
また、徒歩圏内には調布飛行場や武蔵野の森公園があり、観戦と合わせて散策を楽しむ人も少なくありません。車で訪れる場合は近隣の臨時駐車場やコインパーキングを利用できますが、混雑時は公共交通機関の利用が推奨されています。
このようにアクセス環境が整っているため、首都圏各地からの来場もスムーズに行える点が魅力です。
混雑とアクセスのコツ
イベント時は混雑しやすいので早めの到着が安心。特に人気の試合や大型コンサートの日は、開演1時間前でも駅や周辺道路が混み合うことがあります。時間に余裕を持って行動し、事前に交通ルートを確認しておくと安心です。
また、帰りはカフェやコンビニで軽く休憩しながら時間をずらすと、駅の混雑ピークを避けられます。スマートフォンでリアルタイムの混雑情報をチェックするのもおすすめです。
さらに、イベント終了後は臨時列車が運行されることもあるので、事前に京王線の運行情報を確認しておくとよりスムーズに移動できます。
FC東京と東京ヴェルディ、2クラブのW本拠地としての活用
味スタはJリーグでも珍しい「2チームのホームスタジアム」です。
FC東京・東京ヴェルディ共に本拠地として利用
両クラブがホームとして使用し、スケジュールを調整しながら試合を開催しています。試合開催日は互いのリーグ戦やカップ戦、さらには代表戦などのスケジュールを踏まえて慎重に組まれています。
FC東京の試合では青と赤のフラッグがスタンドを彩り、活気ある応援が響き渡ります。
一方、東京ヴェルディの試合では緑を基調とした演出で、サポーター同士の一体感が生まれます。
同じ施設を共有していても、試合の日には雰囲気がガラリと変わり、それぞれのチームカラーや文化が感じられるのが魅力です。
また、施設管理者とクラブ運営側が協力して設備やグラウンドの状態を最適に保つよう努めており、1年を通して高い品質のスタジアム体験が維持されています。
チームカラーと装飾の違い
FC東京は青赤、ヴェルディは緑と、試合ごとにカラーが変わるのも見どころです。スタジアム全体がそのチームのテーマカラーに染まり、照明演出や横断幕、スタッフの制服まで統一感をもってコーディネートされます。
試合当日は、スタンド席にもチームカラーのフラッグやバナーが掲げられ、まるでチーム専用スタジアムのような雰囲気に。
ファン同士の連帯感を高めるだけでなく、初めて訪れた人にも一体感を感じさせる演出がされています。夜の試合ではライトアップの色までチームカラーに合わせて変更されることもあり、写真映えする光景としてSNSでも話題になることが多いです。
サポーター文化の違いと共存
応援スタイルが異なる2チームが共存しており、地域全体でサッカー文化を楽しめる空間となっています。
FC東京のサポーターは情熱的なコールやリズミカルなチャントでスタンドを盛り上げ、試合前後には青赤のユニフォームをまとったファンが街中を彩ります。
一方、東京ヴェルディのサポーターは伝統を重んじ、緑の旗やバナーを掲げてチームへの敬意を表す落ち着いた応援スタイルが特徴です。
両者のスタイルは異なりますが、互いを尊重し合う空気があり、スタジアム外でもフレンドリーな交流が生まれています。
また、両チームが共催する地域清掃活動や子ども向けサッカー教室などを通じて、クラブの枠を超えたコミュニティづくりが進んでいます。こうした文化的な共存が、味スタならではの温かく多様な雰囲気を生み出しているのです。
スポーツ以外での活用事例

サッカー以外にも多彩なイベントが行われています。
大型コンサート・音楽フェス
B’zやback numberなどのライブも行われた事があります。広々とした空間で音楽を満喫できますよ。
スタジアムならではの迫力ある音響と、開放的な屋外空間が相まって、観客全体が一体となる感動的なステージが生まれます。
夜にはライトアップや花火演出が加わり、幻想的な雰囲気に包まれることも。アーティストによっては特設ステージや360度ビューのセットが組まれるなど、味スタならではのスケール感を活かした演出が特徴です。
さらに、音楽フェスでは複数アーティストが参加し、飲食ブースやキッチンカーが並ぶお祭りのような雰囲気を楽しむことができます。
ラグビーW杯2019の会場
世界中のファンが集まり、日本のスポーツ文化を発信する場となりました。試合期間中は国内外から多くの観客が訪れ、会場周辺はまるで国際的な交流拠点のような熱気に包まれました。
海外メディアからも高い評価を受け、運営の円滑さや観客のマナー、ボランティアのホスピタリティなどが話題となりました。
また、地元商店街や飲食店も特別メニューや応援企画を展開し、地域全体が大会を盛り上げるムードに。大会終了後もその経験が地域イベントの運営力向上に活かされ、スタジアムが国際大会に対応できる施設としての信頼を確立しました。
災害時の避難拠点としての役割
スタジアムは、通常のイベント開催だけでなく、非常時には避難場所や物資の集積拠点としても活用されています。
広大な敷地と整った設備を活かし、人の動きや安全面を考慮した導線設計が行われるなど、地域の安心を支える場としての役割も担っています。
屋外での待機スペースや分散受付の仕組みなど、スムーズな対応ができる体制が整えられており、防災や緊急時のサポート拠点としても地域から信頼を集めています。
「味スタ」の呼び名が定着した理由
発音しやすく覚えやすい「味スタ」は、メディア報道やSNSを通じて広まり、地元でも愛される呼称になりました。
その背景には、シンプルで口に出しやすい響きだけでなく、ファンや地域住民の間で自然に浸透していった過程があります。サッカー中継でアナウンサーが頻繁に使うようになったことや、SNSでの投稿タグとして定着したことも大きな要因です。
また、スタジアム周辺では商店街や交通案内にも「味スタ」の表記が見られるようになり、地元の生活に溶け込んでいきました。
さらに、イベントポスターやチケット、観戦グッズなどにも「味スタ」という略称が積極的に使われたことで、世代を問わず認知が広がりました。いまでは東京を象徴するスタジアムのひとつとして、「味スタ」と聞けば誰もが思い浮かべるほどの親しみある存在になっています。
将来的に名称が変わる可能性はある?
命名権契約は更新制のため、将来的に変更の可能性もありますが、すでに「味スタ」が広く定着しているため継続の見込みが高いといわれています。
実際、これまでの契約更新では名称の変更案が出たこともありましたが、地域住民やファンの支持の強さから現名称の継続が選ばれてきました。
また、味の素と東京都の間で築かれた信頼関係も深く、スタジアム運営や地域貢献活動の面でも両者の協力体制が安定しているのが現状です。
今後も社会情勢や企業戦略によって命名権の再募集が行われる可能性はありますが、「味スタ」という愛称は文化として定着しており、仮に企業名が変わっても親しまれる名称として残り続ける可能性が高いでしょう。
ネーミングライツが採用されている主なスタジアム一覧
ネーミングライツ(命名権)を導入しているスタジアムは全国各地にあり、企業と地域の連携によって親しまれています。以下に代表的な施設をご紹介します。
- 日産スタジアム(神奈川県横浜市)
正式名称は「横浜国際総合競技場」。自動車メーカー・日産自動車が命名権を取得しています。 - パナソニックスタジアム吹田(大阪府吹田市)
ガンバ大阪のホームスタジアムで、家電メーカーのパナソニックが命名。 - ヨドコウ桜スタジアム(大阪府大阪市)
セレッソ大阪の本拠地で、淀川製鋼所(ヨドコウ)が命名権を取得。 - エディオンピースウイング広島(広島県広島市)
2024年に完成した新しいサッカースタジアム。エディオンが命名権を取得。 - ベスト電器スタジアム(福岡県福岡市)
アビスパ福岡のホームスタジアム。家電量販店ベスト電器が命名。 - 京セラドーム大阪(大阪府):正式名称「大阪ドーム」2006年から京セラ株式会社が命名権を取得し、「京セラドーム大阪」という通称で知られています。
これらのスタジアムやドームでは、企業名が施設名に含まれることで企業の知名度向上と地域貢献の両立が図られています。名前は変わっても、地域に愛されるスタジアムであることに変わりはありません。
Q&A よくある質問

Q1:味の素スタジアムと東京スタジアムは別ですか?
A:同じ施設で、正式名称が東京スタジアム、愛称が味の素スタジアムです。
Q2:命名権はいつまで?
A:数年ごとに更新され、現在も継続中です。
Q3:「味スタ」という略称はいつから?
A:2000年代後半からJリーグ中継やSNSで自然に広まりました。
Q4:他に命名権を持つスタジアムは?
A:日産スタジアム、パナソニックスタジアム吹田など全国にあります。
まとめ
味の素スタジアムと東京スタジアムは同じ施設であり、「味スタ」という呼び方は地域に根ざした愛称として定着しています。
2003年の命名以来、サッカーやコンサート、地域イベントなど多岐にわたって活用され、東京のスポーツ・文化・コミュニティを支える象徴的な存在となりました。
スタジアムは単なる競技場にとどまらず、地域住民の交流や教育、災害時の支援拠点など多方面で社会に貢献しています。
近年ではデジタルチケットやスマートアクセスなどの新技術も導入され、より快適で環境に優しい施設へと進化を続けています。
これからも人とスポーツ、そして地域をつなぐ大切な場所として、東京の街と共に歩み続けることでしょう。是非参考にしてみて下さいね。