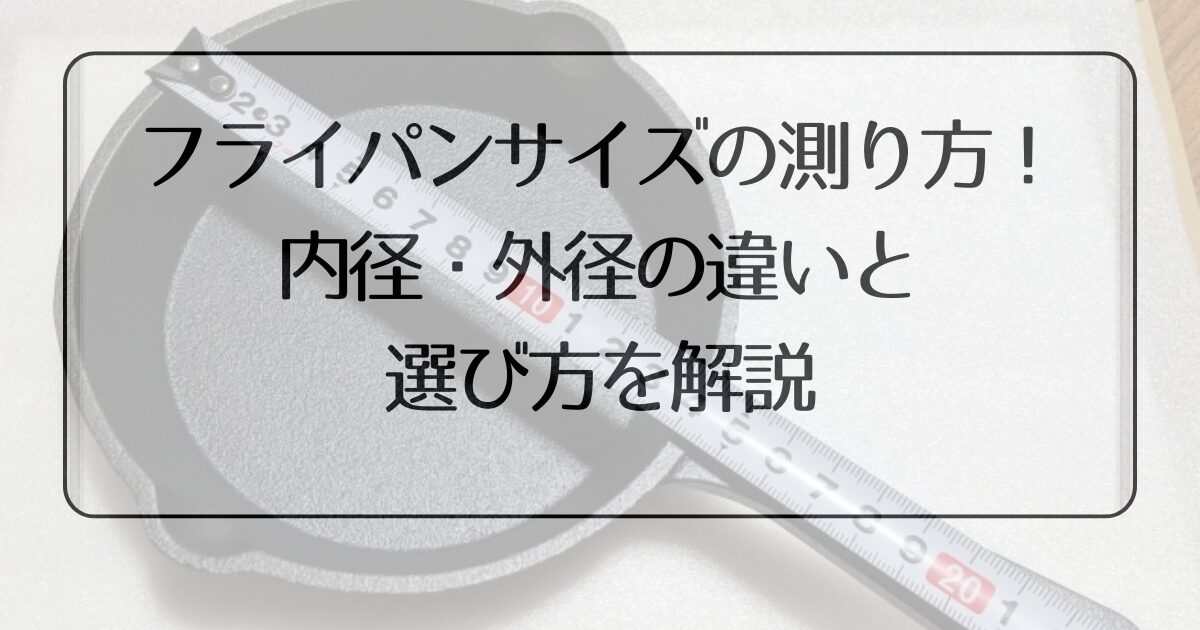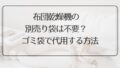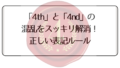フライパンを購入するとき、または後から蓋を購入する際にフライパンを測りながら「このサイズで本当にいいの?」と悩んだことはありませんか?
サイズの表記には「内径」や「外径」などがあり、意外と分かりにくいものです。適切なサイズを選ぶことで、料理のしやすさや収納のしやすさが格段に向上します。
この記事では、フライパンのサイズの測り方や選び方、人気ブランドのサイズ展開まで詳しく解説。最適なフライパンを選び、快適な料理時間を手に入れましょう!
フライパンのサイズとは?

フライパンを選ぶとき、サイズはとても重要なポイントです。適切なサイズを知ることで、料理がしやすくなり、収納にも困りません。ここでは、フライパンのサイズの基本をわかりやすく解説します。
フライパンのサイズ表記の基本
フライパンのサイズ表記は、主に直径(cm)で示されます。多くのメーカーでは、フライパンの上部の内径を基準にサイズを決定していますが、ブランドや種類によって異なることがあります。
一般的にフライパンのパッケージや商品説明には、直径に関する情報が記載されており、これを基準に選ぶことが重要です。
内径と外径の違い
内径はフライパンの内側の幅を表し、、実際に調理できる範囲を示します。
対して外径はフライパン全体の直径の幅を指し、厚みやリム部分を含むことが特徴です。取っ手部分を含まないのが一般的ですが、一部の特殊な形状のフライパンでは外径を基準にサイズ表記されていることもあります。
内径と外径の違いを理解しておくと、購入時に調理スペースや収納スペースを考慮しやすくなります。
サイズの単位:cmについて
フライパンのサイズはセンチメートル(cm)で表記されます。例えば「26cmのフライパン」と記載されている場合、一般的には内径26cmを指します。
ただし、メーカーごとに若干の違いがあるため、購入前に確認することをおすすめします。また、一部の海外ブランドではインチ(inch)表記が用いられることもあり、1インチ=約2.54cmの換算でサイズを確認することが大切です。
サイズを選ぶ際は、調理する食材の量やキッチンの収納スペースも考慮しながら選びましょう。
フライパンのサイズ測り方
フライパンのサイズを測る方法を知っておくと、購入時に失敗しにくくなります。ここでは、直径や深さの測り方、必要な道具について詳しく解説します。
フライパンの直径の測り方
フライパンのサイズを測るには、上から見て最も広い部分を測定します。メーカーによって内径または外径を基準にしているため、使用するフライパンがどのサイズ基準なのか確認しましょう。
また、フライパンの形状によっても測定方法が異なることがあります。例えば、リムの有無や側面の傾斜角度によって、見た目のサイズと実際に調理できる範囲が異なるため、購入時には商品説明や実際の測定を行うことが大切です。
深さや蓋のサイズ測定方法
フライパンの深さは、側面の高さを測ることで確認できます。浅めのフライパンは炒め物に適しており、深めのものは煮込み料理や揚げ物に向いています。
また、フタを購入する際には、フライパンの内径に合ったものを選ぶことが重要です。フタは外径ではなく、内径に合ったサイズのものを選びましょう。
フタの形状にも注意が必要で、ドーム型のものは蒸気を効率的に循環させる効果があり、平らなフタは食材に均等に圧力をかけるのに適しています。
サイズ測定に必要な道具
正確なサイズを測るためには、メジャーや定規を使用するのが一般的です。特に、深さを測る際には、垂直に測るように注意しましょう。
加えて、電子ノギスを使うと、より細かい測定が可能になります。また、キッチンスケールを使用してフライパンの重さを測定し、自分の調理スタイルに合ったサイズを選ぶのも一つの方法です。
さらに、収納スペースとの兼ね合いを考慮し、事前に保管場所の寸法を測っておくことで、無駄なくスペースを活用できます。
人気ブランドのフライパンサイズ一覧

フライパンはブランドごとにサイズ展開が異なります。ここでは、人気ブランドのフライパンサイズを比較し、購入時の参考になる情報をまとめました。
ティファールのフライパンサイズ
ティファールのフライパンは、多くの場合20cm、24cm、26cm、28cm、30cmのサイズ展開があります。
モデルによって異なるので、購入前に確認が必要です。ティファールは特に取っ手が取り外せる「インジニオ・ネオ」シリーズが人気で、収納がしやすく、複数のサイズを揃えるのに適しています。
また、フッ素加工が施されたモデルが多く、焦げ付きにくい仕様になっているため、初心者にも扱いやすいのが特徴です。
ニトリのフライパンサイズ
ニトリのフライパンは、主に18cm、20cm、26cm、28cmなどのラインナップがあり、コストパフォーマンスに優れています。
特に「軽量フライパン」シリーズは、片手でも扱いやすい軽さを実現しており、毎日の料理に便利です。IH対応モデルも豊富で、価格帯もリーズナブルなため、幅広いユーザーに人気があります。
また、独自のマーブルコーティングを採用した製品もあり、耐久性と焦げ付きにくさを兼ね備えています。
ステンレス製やセラミック製のサイズ比較
ステンレス製のフライパンは重厚感があり、24cm~30cmのサイズが主流です。熱伝導が比較的ゆっくりで均一に熱が伝わるため、じっくり焼き上げる料理に適しています。
特にプロ仕様のモデルでは、3層構造や5層構造になっているものが多く、保温性に優れています。一方、セラミック製のフライパンは比較的軽く、20cm~28cmのサイズ展開が多い傾向にあります。
セラミックコーティングにより、少量の油でも調理が可能で、ヘルシー志向の方に人気です。ただし、高温での空焚きには注意が必要で、適切な手入れをすることで長持ちさせることができます。
フライパンのサイズ選び方
フライパンのサイズは、調理のしやすさに直結します。料理の種類や家族構成に合ったサイズを選ぶことで、より快適に調理ができます。
料理の用途に合わせたサイズ選び
料理の種類に応じて適切なサイズを選ぶことが重要です。例えば、オムレツや目玉焼きには20cmのコンパクトなサイズが適しており、素早く均一に火を通すことができます。
一方、炒め物や焼き魚には26cm以上の広めのフライパンを選ぶと、食材を動かしやすく、焦げ付きにくい調理が可能になります。
さらに、パスタや煮込み料理には28cm以上の深型フライパンが適しており、一度に多くの量を作れるため、効率的に調理ができます。
家族構成に応じたおすすめサイズ
1~2人暮らしなら20cm~24cmが最適で、収納スペースを取りすぎず、1食分の調理がしやすいサイズです。
3~4人家族なら26cm~28cmがバランスの良いサイズで、炒め物や揚げ物など、幅広い料理に活用できます。
5人以上の家庭なら30cm以上のフライパンを選ぶと、一度に多くの食材を調理できるため、時短につながります。
また、家族が増えることを見越して、大きめのフライパンを選ぶのも良い選択肢です。
IH対応やガスの熱源別のサイズ
IH調理器では底面が広く、熱を均等に伝えるものが適しています。そのため、IH対応のフライパンは26cm以上の平らな底を持つモデルを選ぶと、熱効率が高くなりやすいです。
一方、ガスコンロでは火力の強弱を調整しやすいため、底面が丸みを帯びたデザインのものも使用可能です。
特に、直火での調理では熱が外側にも広がりやすいため、サイズが大きくても火が均等に入る工夫がされています。
さらに、ガスコンロでは小型のフライパンも使いやすく、用途に合わせた使い分けが重要になります。
フライパンのサイズによる調理方法の違い

フライパンのサイズによって、作れる料理や調理の仕方が異なります。ここでは、小サイズ・大サイズのフライパンの特徴と、それぞれの活用法について紹介します。
小サイズのフライパンでできる料理
小さなフライパン(20cm以下)は、一人分の調理や、目玉焼き・オムレツなどのシンプルな料理に向いています。
また、小型のフライパンは熱が均一に伝わりやすいため、食材の焼きムラが少なく、調理時間も短縮できます。
さらに、持ち運びがしやすく、アウトドアやキャンプでも活躍します。少量の炒め物やパンケーキ作りにも便利で、朝食や軽食を手軽に作るのに適しています。
大サイズのフライパンの活用法
大きなフライパン(28cm以上)は、大量の炒め物や、パエリア・ハンバーグなど複数人分を同時に調理するのに適しています。
また、大きな調理面を活かして、肉や魚を丸ごと焼いたり、大量の具材を一度に炒めたりするのにも便利です。
さらに、ソースを絡めるパスタ料理や、煮込みハンバーグなどの煮込み料理にも活躍します。大サイズのフライパンは、鍋の代用として使えることもあり、調理の幅を広げるアイテムのひとつです。
サイズによる料理のメリットとデメリット
小サイズは軽くて扱いやすいですが、一度に調理できる量が限られます。特に、一人暮らしや少量の調理には最適ですが、家族向けの食事には向いていません。
一方、大サイズのフライパンは、一度にたくさん調理できるため、大人数向けの料理や作り置きに便利ですが、収納にスペースを取る点がデメリットです。
また、大きなフライパンは重量があり、片手で扱うのが難しい場合があります。調理スタイルや収納スペースを考慮して、適したサイズを選ぶことが重要です。
フライパンの耐久性とサイズの関係
フライパンの耐久性は、サイズや材質によっても大きく変わります。熱の伝わり方やコーティングの摩耗など、サイズごとの耐久性について詳しく見ていきましょう。
サイズによる熱伝導率の違い
小さいフライパンは熱伝導が良く、均一に火が通りやすいですが、大きいフライパンは火の当たる部分にムラが出やすいです。
特に、ガスコンロを使用する場合は、火のあたる範囲が狭いため、大きなフライパンでは中心と端で温度差が生じやすくなります。
一方、IHクッキングヒーターではフライパンの底全体が加熱されるため、大きいフライパンでも比較的均一に熱が伝わることが多いです。
フライパンの材質によっても熱伝導率が異なり、アルミ製のものは熱が均一に広がりやすく、ステンレス製は保温性が高いため、食材の余熱調理に向いています。
コーティングの耐久性に影響するサイズ
サイズが大きいフライパンほど、使用頻度が高くなりコーティングの摩耗が早くなることがあります。
また、大型のフライパンは食材の量が増えるため、強火での調理が多くなりがちです。これにより、コーティングの劣化が早まる原因となります。
特にテフロン加工のフライパンは、高温加熱や金属製の調理器具を使うことで、コーティングが剥がれやすくなるため注意が必要です。
セラミックコーティングのフライパンは耐熱性が高く、金属製のヘラでも比較的傷つきにくいですが、硬いスポンジでゴシゴシ洗うと表面が劣化しやすくなります。
長く使うためには、適切な火加減や柔らかいスポンジでの洗浄を心掛けましょう。
サイズ選びと手入れの重要性
適切なサイズのフライパンを選ぶことで、長持ちさせることができます。
例えば、普段の調理で大きすぎるフライパンを使うと、熱効率が悪くなり、食材が焦げ付きやすくなることがあります。適切なサイズを選ぶことで、食材がムダなく加熱され、フライパンの寿命を延ばすことができます。
また、使用後はすぐに洗い、焦げ付きやコーティングの剥がれを防ぎましょう。洗った後は水気をしっかり拭き取り、湿気の多い場所での保管を避けることで、錆や劣化を防ぐことができます。
特に鉄製のフライパンは油をなじませることで、使うほどに耐久性が増すため、定期的にシーズニング(油ならし)を行うと良いでしょう。
フライパンの収納方法とサイズの関連

キッチンのスペースを有効に使うためには、フライパンの収納方法が重要です。サイズごとの収納アイデアや、省スペースでの収納術を紹介します。
サイズに適した収納アイデア
サイズ別に整理できるフライパンラックを活用すると、スムーズに収納できます。
特に、立てて収納できるラックを使用すると、取り出しやすくなり、フライパン同士が重なって傷つくのを防げます。
また、取っ手が外せるタイプのフライパンを選べば、積み重ねても場所を取らず、すっきり収納できます。
壁に取り付けるフックやマグネット式の収納グッズを活用することで、スペースを無駄なく使うことも可能です。
収納時のフライパンの重ね方
大きいものから小さいものへ重ねることで、収納スペースを節約できます。
ただし、重ねる際にはフライパンの表面を保護するため、間にシリコンマットや布を挟むと、コーティングの剥がれを防ぐことができます。
また、頻繁に使用するサイズのフライパンを上の方に配置することで、取り出しやすさが向上します。
さらに、縦置きスタンドを活用すると、重ねずに収納でき、フライパンの傷つきを防ぎながら見た目もすっきりします。
省スペースでのフライパン収納術
壁掛け収納や縦置き収納を活用することで、限られたスペースを有効活用できます。
例えば、キッチンの壁やシンク下にフックを取り付けることで、フライパンを吊るして収納することができ、すぐに手に取れる便利な配置が実現します。
また、引き出しタイプの収納を活用し、仕切りを設けることで、フライパン同士がぶつかるのを防ぎながら効率的に収納できます。
フライパンのサイズや形状に合わせた専用の収納グッズを活用することで、使いやすさを向上させることができます。
料理に合わせたフライパン選び
フライパンのサイズによって、料理の仕上がりや調理のしやすさが変わります。炒め物、揚げ物、一人暮らし向けなど、用途に合わせたフライパンの選び方を解説します。
炒め物に最適なサイズ
炒め物には26cm~28cmの深めのフライパンが適しています。深めのフライパンを使うことで、具材が飛び散りにくく、油の飛び跳ねも防げます。
また、底面が広いフライパンを選ぶと、食材が均一に火が通り、シャキシャキ感を残した炒め物が作りやすくなります。
中華鍋のように丸みのある形状のフライパンを選ぶと、食材がフライパンの端に寄せられ、炒めながら火加減を調整しやすいというメリットもあります。
揚げ物向けの理想的な大きさ
揚げ物には、高さのある20cm~24cmのフライパンがおすすめです。特に、深さが5cm以上のものを選ぶと、油の飛び散りを防ぎ、安全に調理できます。
また、揚げ物専用の温度計が付いたフライパンもあり、適切な温度管理がしやすくなります。鍋型のフライパンを使えば、少ない油でもしっかり揚げられるため、経済的で後片付けも楽になります。
さらに、テフロン加工のものを選ぶと、衣がこびりつきにくく、カラッとした仕上がりが期待できます。
一人暮らし向けのフライパンサイズ
一人暮らしには、コンパクトな20cm~22cmのフライパンが便利です。小さいサイズのフライパンは軽量で扱いやすく、収納スペースも取りません。
また、一人分の食材を適量で調理しやすいため、食材の無駄を減らすことができます。目玉焼きやスクランブルエッグ、焼き魚などの簡単な料理にも最適です。
さらに、取っ手が折りたためるタイプや、取っ手が取り外せるフライパンを選べば、キッチンの収納にも便利です。
フライパンのフタ選びとサイズ

フライパンのフタは、サイズが合わないと蒸気が逃げたり、加熱効率が悪くなったりします。フタのサイズの選び方や、材質ごとの特徴を紹介します。
フタのサイズを合わせる重要性
フライパンのフタは、正しいサイズを選ばないと蒸気が逃げたり、調理効率が下がる原因になります。
フタのサイズは適切なものを選んで使用することで、熱が均一に回り、食材の加熱時間を短縮できるため、料理の仕上がりにも大きく影響します。
さらに、蒸し料理や煮込み料理では、しっかりとフタを閉めることで、食材の水分を逃がさず、ふっくらとした仕上がりを実現できます。
フライパン専用のフタとそのサイズ
メーカーごとに専用のフタが販売されており、最適なサイズを選ぶことができます。フライパンの内径にぴったり合う専用のフタを使うことで、より効率的に調理が可能です。
一部のメーカーでは、複数のサイズに対応する「万能フタ」も販売されており、異なるフライパンで兼用できるタイプもあります。
また、フタのデザインも重要で、シリコン素材のフタは密閉性が高く、熱を逃がしにくいメリットがあります。
フタの材質が料理に与える影響
ガラス製のフタは中が見えるため便利ですが、金属製は耐久性が高いなど、それぞれの特徴を理解して選ぶことが大切です。
ガラス製のフタは、料理の進行状況を確認しやすく、蒸し料理や煮込み料理に適しています。一方、ステンレスやアルミ製のフタは、耐久性が高く、熱伝導が良いため、素早く食材を加熱するのに適しています。
さらに、木製のフタは熱を和らげる効果があり、煮物や低温調理に向いています。料理の種類や調理スタイルに合わせて、最適なフタを選ぶことがポイントです。
まとめ
フライパンのサイズ選びは、料理のしやすさや仕上がりに大きな影響を与えます。適切なサイズを知ることで、調理の効率が上がり、収納もしやすくなります。
この記事では、サイズの測り方や選び方、ブランドごとの違いなどを詳しく解説しました。小さめのフライパンは一人暮らしや簡単な調理に、大きめのものは家族向けや本格的な料理に最適です。
また、収納やメンテナンスの工夫をすることで、長く快適に使うことができます。あなたにぴったりのフライパンを見つけ、毎日の料理をもっと楽しんでくださいね!