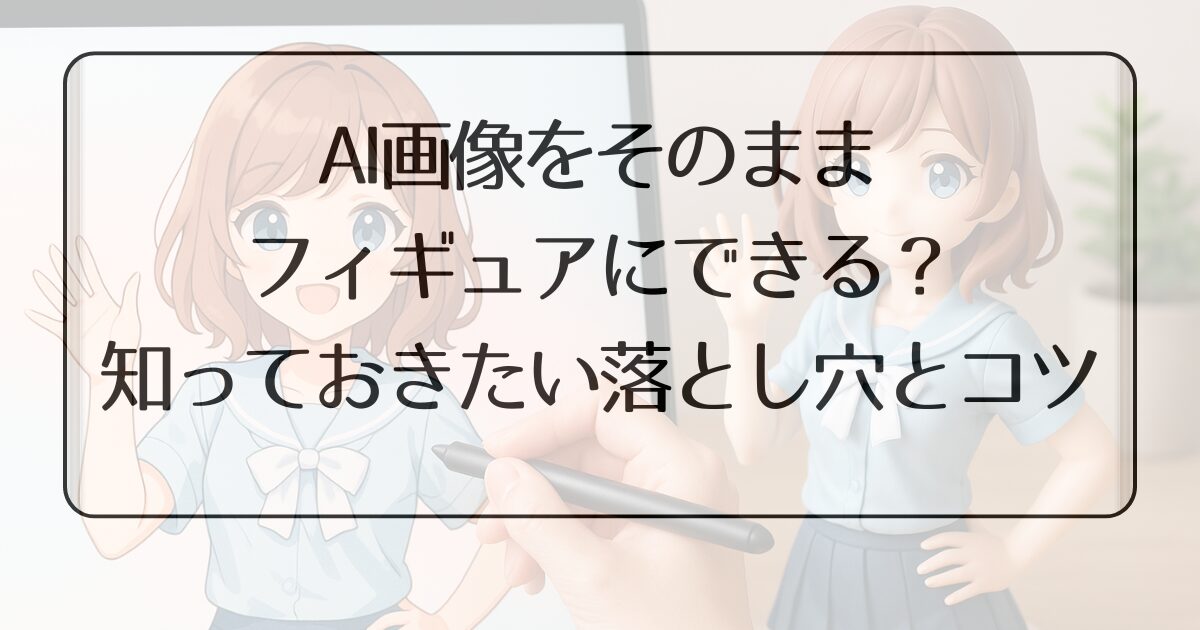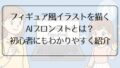最近ではAIを使って美しいイラストを手軽に描けるようになり、「このキャラをそのままフィギュアにしたい!」という声も増えてきました。
でも実は、AIイラストと3Dフィギュア化では、目的や仕上がり、必要な工程などが大きく異なるんです。なんとなく似たイメージを持っていた方も、実際にフィギュアとして形にしたいと思ったときに「え、これじゃ足りないの?」と戸惑うことも。
この記事では、AIイラストと3Dフィギュア化の違いをわかりやすく解説し、実際にフィギュア化を考えている方に向けて、知っておくべき注意点やおすすめの進め方までを丁寧にまとめました。
AIで作った画像を本物の立体物にしたい方や、イラストとフィギュアの違いを知っておきたい方は、ぜひ最後までご覧くださいね。
AIイラストと3Dフィギュア化は何が違うの?
イラストとフィギュア、一見似ているけれど、根本的に目的や出力形式が違うんです。
出力されるものの違い
AIイラストは基本的に平面のデジタル画像として出力されます。JPEGやPNGといった形式で保存され、SNSへの投稿やアイコン、ブログの挿絵、印刷物のデザインなど、幅広いシーンで活用されています。
一方で3Dフィギュアは、立体物として実際に手に取れる形で存在します。これは、デジタル上で作成された3Dモデルデータ(STLなど)をもとに、3Dプリンターなどを使って物理的に造形されるものです。
つまり、AIイラストはあくまで「画面上で楽しむ」ものであるのに対し、3Dフィギュアは「空間に存在し、手に取れる実物」であるという違いがあります。この視点の違いが、出力形式の根本的な違いを生み出していると言えるでしょう。
使用目的や使い道の違い
AIイラストは、SNSのアイコンやブログの挿絵、ポスターやパンフレットのデザインなど、視覚的な印象を与えるためのものです。静止画としての美しさや雰囲気づくりに向いており、特に「見る楽しさ」を重視した使い道が中心となります。
一方で3Dフィギュアは、机や棚に飾ったり、プレゼントとして贈ったり、コレクションの一部として並べたりと、実際に「所有する喜び」や「飾る楽しさ」を感じられるものです。
どちらも創作物であることには変わりませんが、AIイラストが「視覚的な魅力」を届けるものであるのに対し、3Dフィギュアは「実際に触れて楽しむ」という点に大きな違いがあります。活躍する場面も大きく異なってくるため、目的に応じて選ぶことが大切です。
どちらが向いている?用途別の考え方
「世界観を視覚的に表現したい」「デザイン案を素早く形にしたい」「作品としてSNSに投稿したい」といった場合には、AIイラストがとても便利です。短時間で美しいビジュアルを生成できるため、発想をアウトプットする手段として優れています。
一方、「実物として飾りたい」「記念品として誰かに贈りたい」「手元に置いて楽しみたい」といったニーズがある場合は、3Dフィギュアの方が適しています。
たとえばイベントやプレゼント、記念の品として残したいなら、立体化することでより特別な存在になります。どちらを選ぶかは、「完成形として何を求めるか」によって変わってくるんですね。
3Dフィギュア化を考えるときの注意点
フィギュアを作るには、イラストのままでは足りない場合も。しっかり準備しておきましょう。
AI画像はそのまま使えない?
AIで生成した画像をそのまま立体化することは、基本的にはできません。なぜなら、AIイラストは正確な三面図や立体構造を前提として作られていないからです。
特にキャラクターの背面や側面といった、立体化に必要な角度の情報が描かれていないことが多く、3D化の際に大きな障害となることがあります。
また、ポーズによっては身体の一部が隠れていたり、手足のバランスが実際の立体では不自然になったりする場合もあります。そのため、3Dフィギュアに仕上げるには、AI画像をもとに改めて正面・背面・側面などの「設計図」に近い資料を作成する必要があることも少なくありません。単なるイメージ画像としては優秀でも、立体制作には向かない点を知っておきましょう。
著作権や権利の問題
AIで作った画像だからといって、すべて自由に使えるわけではありません。生成に使ったAIツールの利用規約や、学習に用いられた素材の扱いによっては、商用利用や立体物への転用が制限されている場合もあります。
たとえば、利用規約で「生成画像の商用利用禁止」や「製品化には別途許可が必要」と記載されているケースもあるため、注意が必要です。
また、AIが学習したデータに似たキャラクターや既存の作品に無意識に寄せたデザインになっている可能性も否定できません。他人の著作物と似ている場合、意図しなくてもトラブルになることがあります。
特に販売や展示など外部に公開する予定がある場合は、必ず事前に確認してから進めるようにしましょう。個人利用でもグレーなケースがあるため、慎重な判断が求められます。
製作依頼時に伝えるべきこと
3Dフィギュア化を専門の業者やモデラーに依頼する際には、ポーズや服装のディテール、顔の向きや表情など、具体的な要望をしっかり伝えることがとても大切です。AIで作成した画像を「このままでお願いします」と一枚だけ渡しても、造形側が困ってしまうケースがほとんどです。
特に立体物では、正面だけでなく側面・背面の形状も把握する必要があるため、できれば複数の角度からの資料画像や、似た雰囲気の参考資料を用意しましょう。
また「この角度から見たときに映えるようにしたい」「台座はこうしたい」など、完成イメージを明確に伝えることで、仕上がりの満足度も高くなります。依頼する前に、伝えるべき内容を整理しておくとスムーズです。
フィギュア化におすすめの手順とサービス例
初めてでも安心。どんな手順で進めればいいのか、基本の流れを紹介します。
どんなデータが必要になる?
多くの3Dフィギュア制作サービスでは、制作の元となる「三面図(前・横・後ろ)」のイラストや、3Dモデル作成に適したスケッチデータの提出が求められます。これは、立体的な造形を正確に行うために必要な情報で、特に衣装の形状や髪型、パーツの位置関係などを細かく伝えるために不可欠です。
最近では、AIで生成した1枚絵をベースに、後から自分で加筆を加えて三面図に近づける方法や、別のAIツールを使って三方向のイラストを自動生成する方法も増えてきています。
また、元から3D化を想定した構図やポーズでAIイラストを作成することで、後の修正作業が減りスムーズに進められます。
特に、左右対称で全身がしっかり見えるデザインは3D向き。立体化しやすい構図を意識してイラストを用意しておくことも、大切なポイントになります。
個人でも依頼できるサービス
個人でも気軽に利用できる3Dフィギュア制作サービスは年々増えており、初心者でもチャレンジしやすくなっています。たとえば、手軽にオーダー可能な「デジタルフィギュア工房」や、3Dプリント・出力までワンストップで対応してくれる「Rinkak」などが代表的です。
これらのサービスはオンライン上でのやり取りが中心で、完成データの確認や修正依頼もスムーズに行えるのが特徴。SNSなどで実績のある3Dモデラーさんに直接依頼したり、クラウドソーシングサービスで希望に合う方を探すという方法もあります。
自分の予算や納期、デザインのこだわりに応じて、柔軟に選べるのが魅力ですね。初めての場合は、過去の作例をチェックし、やり取りの丁寧な制作者さんを選ぶのが安心です。
費用や納期の目安も知っておこう
3Dフィギュアの制作費用や納期は、依頼する内容や制作手法、使用する素材によって大きく変わります。たとえば、比較的シンプルな形状であれば数万円程度から依頼できることもありますが、細部まで作り込まれたキャラクターや、装飾が多い衣装、ポーズにこだわった造形などになると、10万円〜30万円以上かかることも珍しくありません。
納期も同様に、簡易的なモデルであっても1〜2ヶ月ほどかかるのが一般的です。さらに、フィギュアの実物出力や着色まで含めた場合は、さらに時間が延びることがあります。そのため、誕生日プレゼントや記念品として贈りたい場合などは、制作開始から完成までを逆算して、早めに準備を進めるのがとても重要です。
費用や納期をあらかじめ把握しておくことで、スムーズなスケジュール調整ができ、納得のいく仕上がりにもつながります。
Q&A:よくある疑問にお答えします
Q:AIイラストでもフィギュアは作れるの?
A:作ることは可能ですが、そのままでは情報が足りないことが多いため、追加で三面図を描いたり補足資料が必要です。
Q:著作権が心配…どうしたらいい?
A:AIツールの利用規約を必ず確認し、自作であることや商用利用可であることを明確にしておきましょう。
Q:自分でもモデリングできる?
A:3Dモデリングソフト(Blenderなど)を使えば自作も可能ですが、初心者にはハードルが高いため、まずは依頼や既存サービスの活用がおすすめです。
まとめ|イラストもフィギュアも、それぞれに魅力がある!
AIイラストと3Dフィギュアは、それぞれ異なる魅力を持つ創作の形です。平面だからこそ伝えられる雰囲気、立体だからこそ感じられる存在感――どちらも素敵な表現手段ですよね。
「イラストで想像を広げる楽しさ」と「フィギュアとして手元に置ける喜び」は別物ですが、どちらも自分だけの作品を作る喜びにつながります。今回ご紹介した違いや注意点、進め方などを参考に、目的に合った創作スタイルを選んでみてくださいね。
あなたの「つくりたい!」という気持ちが、素敵な形でカタチになりますように。