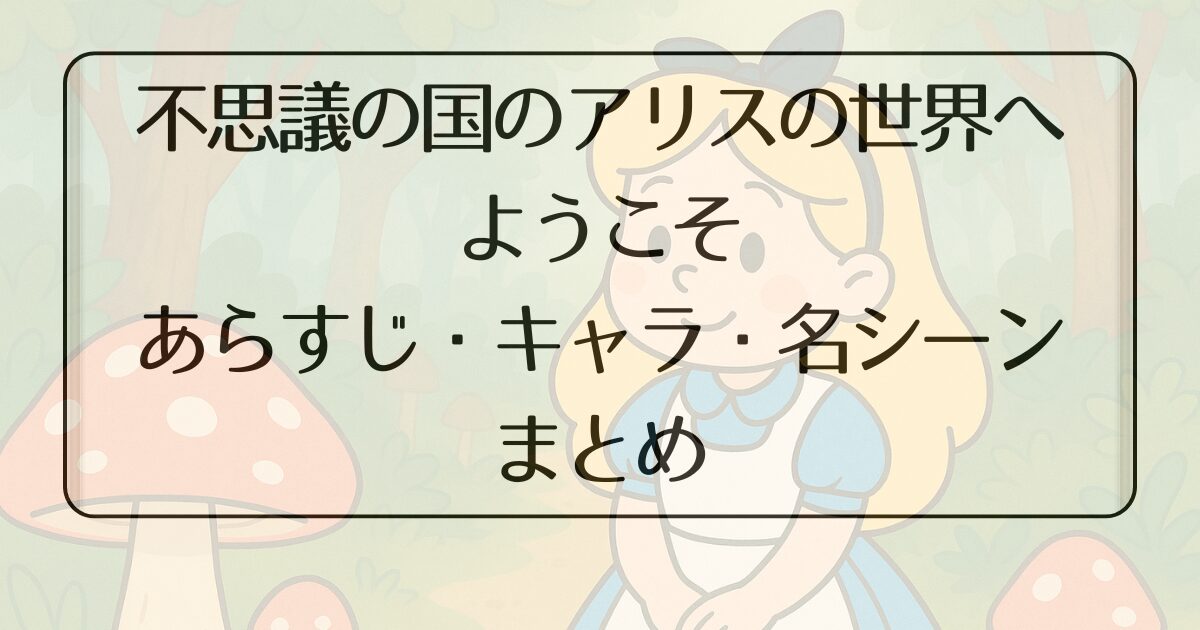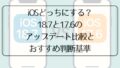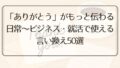子どもの頃に読んだことがあるけれど、内容をすっかり忘れてしまった…という方も多いのではないでしょうか?
実は私もそのひとりでした。久しぶりに図書館でふと手に取って読み返してみたら、驚くほどたくさんの“気づき”が散りばめられていて、「こんなに奥深かったんだ…」と感動したのを覚えています。
『不思議の国のアリス』は、ただの夢物語ではなく、大人になった今だからこそ感じられる魅力がたくさん詰まった作品です。子どもの頃には見過ごしていたような、社会の矛盾や個性の大切さ、自分らしさを模索する姿が、アリスの冒険を通して鮮やかに浮かび上がってきます。
このページでは、忙しい毎日を過ごすあなたでも3分で物語の流れがつかめるように、あらすじをやさしく解説。そのあとで、登場人物の個性や深いメッセージ、物語の背景にある時代性、そして読み終わったあとにもっと楽しめる関連情報まで、女性目線でわかりやすく丁寧にご紹介していきます。
あの頃の自分が見逃していた“本当のアリス”に出会えるかもしれません。ぜひ、アリスの世界をもう一度のぞいてみませんか?
まず知りたい!『不思議の国のアリス』のあらすじを3分で紹介

不思議の国のアリスをイメージした切り絵風シルエット
まずは、アリスの不思議な冒険がどんなものだったのか、サクッと把握してみましょう。
白うさぎを追って穴に落ちるアリス
ある日、退屈していたアリスは、お姉さんと一緒に川辺で本を読んで過ごしていましたが、内容がつまらなくてぼんやりしていました。そんなとき、チョッキを着て時計を手にした白うさぎが「遅刻だ、遅刻だ!」とつぶやきながら目の前を駆け抜けていきます。
その異様な光景に驚きつつも強く興味をひかれたアリスは、思わずその後を追いかけていきました。白うさぎが飛び込んだ大きな穴にアリスも勢いあまって落ちてしまい、長く深いトンネルをゆっくりと落ちていくうちに、やがて不思議でちょっとこわい、けれどワクワクするような冒険が始まっていきます。
大きくなったり小さくなったりの冒険
不思議の国にたどり着いたアリスは、そこにあった小さな扉を通るために、近くに置かれていた「飲んでね」と書かれた小瓶の中身を飲んでみることに。
すると体が急に小さくなり、まるでお人形のようなサイズになってしまいます。逆に、ケーキを食べたときには大きくなりすぎて天井に頭がつかえるほどの巨人に変身。
飲んだり食べたりするたびに体のサイズが変わってしまい、アリスは困惑しながらも、どうにか不思議の国の中を前に進んでいきます。
おかしな住人たちとの不思議な出会い
チェシャ猫や帽子屋、三月うさぎ、芋虫など、個性が強く、どこか風変わりな住人たちが次々に登場します。
チェシャ猫は不意に現れては消える存在で、にやにや笑いながらも「どこに行きたいのかが決まっていないなら、どの道でも同じことだよ」といったような、ふと考えさせられる言葉を投げかけてきます。
帽子屋や三月うさぎとの永遠に続くお茶会では、言葉がかみ合わないやりとりが延々と続き、時間という概念がない世界の不思議さにアリスも困惑します。
芋虫は、アリスに対して「あなたは誰?」と問いかけることで、アリスの心の動揺を引き出します。一見ナンセンスに見えるこうしたやりとりには、「自分とは何か」「自分の考えで物事を判断する大切さ」など、深い哲学的な問いかけが隠されており、大人の読者ほどじんわりと胸に残る場面が多いのが特徴です。
ハートの女王の裁判と目覚めのラスト
物語の終盤、アリスは突如としてハートの女王によって開かれた裁判に呼び出されます。王国中の住人たちが集まる中、無実の罪で裁かれることになったアリスは、その理不尽さに強く違和感を抱きます。
ハートの女王は気まぐれで「首をはねよ!」を連発し、場の空気は常に緊張感に包まれています。やがて、アリスはその世界のあまりのナンセンスさに耐えきれず、「こんなのバカバカしい!」と大声で叫び、堂々と女王に立ち向かいます。
その瞬間、すべてが崩れるようにして現実へと引き戻され、アリスは草の上で目を覚まします。不思議な世界での体験は夢だったのか、それともどこか現実とつながっていたのか――。すべてをふり返りながら、アリスは少しだけ大人びた表情を見せるのでした。
この物語に込められた意味と背景とは?
「なぜ今もアリスは読み継がれているのか?」その答えは、この章に。
ルイス・キャロルと当時の時代背景
作者ルイス・キャロルは、イギリスの数学者・論理学者でありながら、詩人や写真家としても多才な人物でした。本名はチャールズ・ラトウィッジ・ドジソンといい、オックスフォード大学で数学を教えるかたわら、子どもたちとの交流の中から空想的なお話をよく語っていたそうです。
とくに友人の娘である少女・アリス・リデルとの出会いが、あの名作誕生のきっかけとなりました。
この物語が誕生した19世紀後半は、ヴィクトリア朝時代と呼ばれるイギリスの激動期。産業革命による急速な近代化とともに、厳格な道徳観や階級制度が色濃く残っていた時代でもあります。
女性の社会的立場や子ども観にも大きな変化が生まれつつあり、そういった揺らぎの中で書かれた『アリス』は、当時の風潮をユーモラスに反映しながら、子どもたちへの自由な想像の世界を届けたといえるでしょう。
ナンセンスに隠された社会風刺
「ナンセンス文学」として知られるアリスの物語ですが、単なる言葉遊びや奇妙な会話だけでなく、実はイギリス社会への痛烈な風刺がちりばめられています。
たとえば、意味もなく威圧的な態度をとるハートの女王は、当時の支配的な権力者の風刺ともとれますし、帽子屋や三月うさぎとのかみ合わないお茶会は、形式ばかりが重視される社交界への皮肉とも読めます。
理不尽なルールに翻弄されながらも、自分の感性で疑問を投げかけるアリスの姿は、現代を生きる私たちにも共鳴するテーマを含んでいます。
子どもから大人へ、成長の寓話として
体が大きくなったり小さくなったりする描写は、「子どもから大人へ成長していく心と体のギャップ」を象徴しているとも言われています。
自分の体にうまくなじまないもどかしさや、周囲とのズレを感じる違和感は、思春期を迎える多くの人にとって共感できるものです。
アリスがその都度状況に戸惑いながらも、自分なりの判断で行動していく姿は、「正しさ」ではなく「自分らしさ」を模索する過程そのもの。読者は、アリスとともに、成長の中にある混乱と発見の旅を追体験していくのです。
なぜ世界中で長く愛され続けているのか?
決まった正解がないからこそ、読む人それぞれの解釈ができる──それがアリスの最大の魅力です。子どもにとっては夢のような不思議な冒険として、大人にとっては社会や自分自身を映す鏡のように感じられることも。
読むたびに違った視点で受け止められる柔軟さが、アリスを時代や文化を超えて愛される物語にしているのです。
【あわせて読みたい】
「不思議の国のアリスって童話?それとも寓話?」と気になった方へ。
寓話の意味や童話・昔話との違い、有名作品までをやさしく解説した記事もご用意しています。
作品をより深く味わいたい方にぴったりの内容です。
登場人物でわかる!アリスの世界の魅力

キャラクターを知れば、アリスの物語がもっと楽しくなります。
アリス ─ 好奇心と理不尽への戸惑い
素直で探究心旺盛なアリスは、読者にとっての案内役でもあります。どんな状況でも自分なりに考えようとする姿に共感する女性も多いはず。
未知の出来事にも怯まず立ち向かうその姿勢には、強さと柔軟さの両面が見られます。常識が通じない世界の中でも、自分の感覚を信じながら進んでいく姿が、読者の心に自然と響いてくるのです。
白うさぎ ─ 忙しそうな導き手
「遅刻だ、遅刻だ!」と時計を見ながら慌てる白うさぎ。アリスを不思議の国へ導く存在として、物語のきっかけを作ります。
彼のせわしない動きや発言は、物語のテンポを一気に加速させ、読者の興味を引きつけるスイッチのような役割も果たしています。彼の登場がなければ、アリスの冒険は始まらなかったのです。
チェシャ猫 ─ 哲学的な道案内
ニヤニヤ笑いながら突然現れたり消えたりするチェシャ猫。物事の本質をつくような言葉を投げかけてくる名キャラです。
彼の存在は、アリスに限らず読者にも「選択」や「考えることの大切さ」を問いかけてくれます。不可思議な世界の中で、唯一アリスにヒントを与えてくれる存在ともいえます。
帽子屋と三月うさぎ ─ 永遠に続くお茶会
時間が止まった世界で繰り広げられる奇妙なお茶会。会話のテンポややりとりの妙が印象的です。ふたりの登場人物は、とにかく自由奔放でルールに縛られないやりとりを続け、アリスを混乱させますが、それが逆に“常識とは何か”を考えさせる場面にもなっています。
ハートの女王 ─ 怒りっぽく支配的な存在
「首をはねよ!」が口癖のハートの女王。理不尽の象徴として描かれ、アリスとの対比が印象に残ります。
彼女の横暴さや感情的なふるまいは、権力の持つ危うさや、言葉による支配の怖さを暗示しているとも読めます。そんな女王にひるまず立ち向かうアリスの姿が、よりいっそう輝いて見えるのです。
物語の流れをざっくり時系列で追う
「どんな順番で出来事が起きたか」を整理したい方におすすめ。
- 白うさぎを追って地面の穴に落ちる
- 小さな扉に入るため体のサイズを変える
- 涙の池や動物たちとの出会い
- 芋虫や帽子屋など個性的な住人たちと交流
- ハートの女王の裁判
- 「これは夢だった」と目覚める
知っておきたい!名言・名シーンまとめ

一度は聞いたことのあるあのセリフも、実はアリスから。
- アリス:「ここはどこ? 私は誰?」
- チェシャ猫:「どの道を行っても、行きたい場所が決まっていないなら同じこと」
- ハートの女王:「首をはねよ!」
- 芋虫:「あなたは、誰なの?」
- 帽子屋:「時間に殺されるよりは、時間を殺した方がいいさ」
深い意味がありそうで、考えるほどに不思議な言葉たちです。登場人物たちが投げかけるセリフは、ただの言葉遊びのようでいて、実は読む人の心に問いを投げかけてくれる存在でもあります。何気ない一言が、現実の私たちの価値観を揺さぶるきっかけになることもあるかもしれません。
「不思議の国のアリス」はどう読むべき?初心者さん向け読書ガイド
アリスの世界に興味はあるけど、「難しそう」「原作は古い英語で読みにくいのでは?」と感じている方も多いかもしれません。このセクションでは、そんな方に向けて無理なく楽しむ読み方のヒントをご紹介します。
どの訳本を選ぶのがいい?
はじめて読むなら、現代語訳でやさしく訳された文庫版や、子ども向けに編集された絵入りのバージョンがおすすめです。翻訳者によって文体の印象がかなり変わるので、書店やネットのレビューを参考に自分に合った1冊を選んでみてください。
また、注釈付きやイラスト解説付きの本を選ぶと、背景知識も補えるためより深く楽しめます。
絵本・漫画で入門するのもアリ?
もちろんアリです!絵本や漫画版は、物語の流れを視覚的に理解しやすく、アリスの世界観に親しむきっかけとしてぴったりです。
子ども向けとあなどらず、大人が読んでも十分に楽しめるよう工夫された作品も多数あります。近年ではアート性の高い大人向けのグラフィックノベル版も人気で、コレクションとしても楽しめます。
映画から入っても楽しめる?
映画やアニメーションでアリスに触れるのも良い入り口です。ディズニーのクラシックアニメは親しみやすく、ティム・バートン監督の実写版は幻想的で大人向けの雰囲気。どちらも原作とは違った解釈が加えられているので、比較しながら楽しむのも一興です。
さらに、舞台化された作品や海外ドラマの中でアリスの世界をモチーフにした演出を見るのも、世界観をより広く楽しむ手段になります。
関連作品やコンテンツでさらに楽しむ
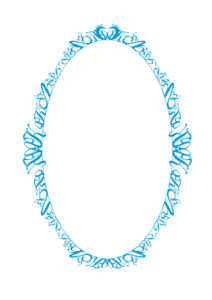
原作をきっかけに、アリスの世界は広がっていきます。
- 続編『鏡の国のアリス』もあわせて読みたい
アリスが鏡を通り抜けて別の不思議な世界に迷い込む続編で、新しい登場人物やルールの違う世界観を楽しめます。前作とはまた違った成長と気づきが描かれており、読み比べると奥深さが増します。
- ディズニーアニメやティム・バートン監督の実写映画も人気
映像ならではの演出や色彩表現、音楽によって、アリスの世界観がよりファンタジックに楽しめます。ティム・バートン版では、独自の解釈で再構築されたストーリーが注目を集めました。
- グッズやカフェ、アリス展などのリアルイベントも多数
食器や雑貨、アクセサリーなどのアリスモチーフ商品はもちろん、世界観を再現したカフェや展示会も人気。写真映えする空間や、限定アイテム目当てに訪れるファンも多く、アリスの魅力は本だけにとどまりません。
「不思議の国のアリス」Q&A|よくある質問まとめ
なぜ子どもだけでなく大人にも人気なの?
ナンセンスで奇妙な展開の中に、「自分らしさ」や「社会の矛盾」を考えさせられるからです。物語をただのファンタジーとして楽しむだけでなく、権力への風刺や理不尽さに対する疑問など、深く読み込むことで大人ならではの視点が広がります。
また、アリスのように「自分は何者か」と考える過程は、誰にとっても共通のテーマであり、多くの人の心に響くのです。
アリスの冒険は夢?現実?
物語のラストでは夢から目覚めますが、「夢か現実かはあなた次第」という含みも感じさせます。
作中には何度も現実と幻想が交錯するような描写があり、「夢の中で得た気づきが、現実の世界に影響するかもしれない」といった余韻を読者に残してくれます。
一番人気のキャラは?
チェシャ猫や帽子屋が特に人気。ちょっと変わっていて、でも魅力的な存在です。チェシャ猫の含みある発言や、帽子屋の独特なテンポの会話は、読者の印象に強く残ります。
また、誰もが常識にとらわれず自由にふるまっているところも、魅力のひとつと言えるでしょう。
続編はある?『鏡の国のアリス』って?
続編として『鏡の国のアリス』があります。アリスが鏡を通って別の世界に行く新しい冒険の物語です。
前作よりもさらに抽象的で、チェスのルールに沿って進む不思議な展開が楽しめます。キャラクターの言葉遊びや構造の妙も評価されており、文学的にも高い評価を受けている作品です。
アリスを読んだ後におすすめの本は?
『オズの魔法使い』『ムーミン』『星の王子さま』など、幻想的で哲学的な童話もおすすめです。
それぞれに独自の世界観と人生に対する優しいまなざしがあり、アリス同様に読み手の心に長く残る作品ばかり。どの作品も、世代を問わず楽しめる魅力があります。
まとめ|アリスの世界は、今でも色あせない名作
『不思議の国のアリス』は、子ども向けの物語でありながら、大人の心にも深く響く名作です。理不尽さや不条理、成長の痛み、そして自分自身を見つめ直すきっかけを与えてくれるこの物語は、時代や国を超えて多くの人に愛されています。
アリスが体験する出来事のひとつひとつには、子どもだけでなく大人が感じる社会の窮屈さや矛盾、そして自我の目覚めが象徴されており、読むたびに新しい気づきを与えてくれます。
私自身、久しぶりに読み返したとき、子どもの頃には気にも留めなかったセリフや展開に、妙にハッとさせられたことを思い出します。
アリスが戸惑いながらも前に進もうとする姿に、まるで自分を重ねるような感覚がありました。大人になった今こそ、この物語の持つ“もう一つの顔”に気づけるのかもしれません。
ファンタジーの世界に迷い込みながらも、実はとても現実的なテーマに触れられるのがアリスの魅力。感情に素直で、物事に疑問を持ちながら進んでいくアリスの姿に、勇気や希望をもらえる方も多いのではないでしょうか。
ちょっと疲れた日や、現実から少し離れたいとき、もう一度アリスに会いに行ってみてはいかがでしょうか? きっと、かつての自分に出会えるような感覚や、新しい視点を得るきっかけになるかもしれません。
きっと新しい発見がありますよ。ぜひ参考にしてみてくださいね。